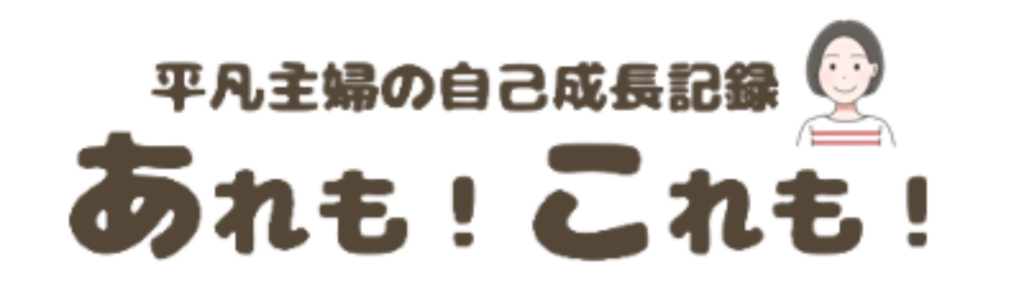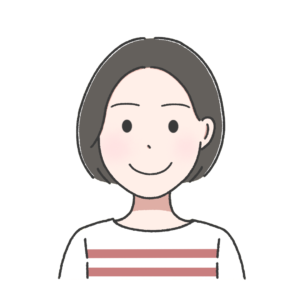
こんにちは。ココです。
貯金が増えないのが結婚以来の悩みです。
長らく実家暮らしだった独身時代は少々派手な使い方をしても貯まる貯まる・・・。(ちゃんと家にお金は入れてましたよ!)
結構な額の貯金ができていましたが、そんなホクホクな状況は結婚して正社員を辞めたのを機に一転しました。
「あれ・・・?足りない。貯金をちょっと下ろさないと・・・。」
それは結婚7年目にもなる現在でもあまり変わらず。子供も大きくなってくるし、さすがに将来への不安を感じるようになってきたので、新年を機に家計管理を大きく見直すことにしました。
そこで重要になってくるのが特別費というもの。
この記事では特別費がどういうものかというのと、特別費を踏まえた上での年間予算の決め方についてざっくりと説明しています。
まだトライ&エラーの最中ではありますが、どなたかのお役に立てれば幸いです。
これまでの家計状況
うちは夫と私のお給料で生計を立てています。夫からは全額渡されるわけではなく、必要な分を入れてもらうスタイルです。その中でやりくりし、余ったら貯金。というやり方でやってきました。
が、これがまぁ余らない (^ ^ ;
以前の記事でパーキンソンの法則のことを書きましたが、お金にもしっかりこの法則が働いているんだなぁと思います。
貯金は長男(4歳)が生まれる前までに貯めていた数十万円があるのですが、その貯金額は増えては減っての繰り返しで数年経った今もあまり変わらず(むしろちょっと減った・・・)。
毎月ギリギリ足りるか足りないかという状況を何年も続けてきました(足りない時は貯金を下ろす _l ̄l●lll )。
一応、資産運用はしている
貯金が一向に増えない状況が続いているのですが、実はそんな状況を見越して毎月一定額をNISAをはじめとした資産運用に回しています。自動積立なので家計がギリギリだろうがなんだろうが強制的に、というわけです。
あとは児童手当と長らく普通預金に放置していた独身時代の貯金なども資産運用に回すようにしました。
それらは順調に増えており、このまま積み立て続ければ子供たちの学費や老後の生活費として備えることができるだろうと思っています。
余談ですが、独身時代の貯金はもっと早くに資産運用に回しておけばよかったと本当に後悔しています (T_T)
10年早く投資できていたならどれだけ増えていただろうと・・・。
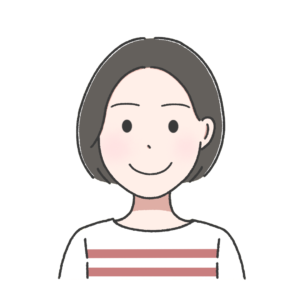
この記事を読んでいる方で、普通預金に大きなお金が眠っている方は今すぐ投資を始めることをおすすめします。
でも普通預金もある程度は必要
投資に回しているお金は長い期間をかけてそこそこの金額になってくれるであろうと見越していますが、普通預金にもある程度の金額は残しておく必要があります。
以前、車の故障で急に数十万円の出費がありました !(꒪ꇴ꒪〣)
その時は別のルートのお金でなんとか乗り越えることができたのですが、車以外にも(あまり考えたくはありませんが)事故や病気、災害などのアクシデントはいつ起きるかわかりません。こういうアクシデントが起きた時にも最低限対応できるだけのお金は持っておきたいところです。(投資信託などは引き出すのに時間がかかることもあるのです。だから普通預金がもう少しほしい。)
現在はほとんど貯金ができていない状況なので、せめて月々1万円は安定して貯金できるようになるのが目標です。
家計簿の再開を決意
実はこんな私でも最近まで一応家計簿は付けていました。
でも今思うと、一向に貯金が増えない状況なのにやり方を見直すこともなく付け続けていた家計簿って本っっ当に意味なかったなぁと思います (^ ^ ;

もっと早くやり方を見直すべきでした。惰性でただただ付けていた労力と時間が本当に無駄だった・・・。
というわけで、新年ということもあり、重い腰を上げて家計簿の付け方(家計管理のやり方)を見直すことにしました。
最初はいわゆる袋分け家計簿(1週間分の予算を封筒に分けて、そこから使っていくやり方)を考えていましたが、普段の買い物はほぼほぼキャッシュレスですし、お金をテーブルの上に並べて細かい作業をするのは性に合わないと思ったので、やっぱりアプリで管理することにしました。
実はアプリでも袋分けっぽいことができるこんなアプリがあったのです。今回はこれでしばらく試してみたいと思います。

特別費というものを知る
「いつもお金を使い切ってしまうということは予算設定に問題があるんじゃないか?」と思い、予算を徹底的に考え直すことにしました。
「でも面倒なことはしたくない・・・。どうしたらシンプルかつちゃんと管理ができるようになるんだろう。」とネットで色々検索していると、ある単語を見つけました。
そう、それが「特別費」です。
(常識だったりして?私はこれまで知らずに生きてきました (T_T) )
ある方のブログで、家計は「固定費・変動費・特別費」の3つだけ考えれば良いという記事を読みました(記事を紹介したいところですが、すみません忘れました (> <) )
そして、特別費をいかにコントロールできるかが家計管理が上手くいくかにかかっているということも書かれていました。
特別費というのは人によって定義は少し違うかもしれませんが、私は「生活に必ずしも必要ではない、または自分の意思で金額がコントロールできるもの」と定義しました。旅行代、レジャー費、交際費などが該当すると私は考えています。
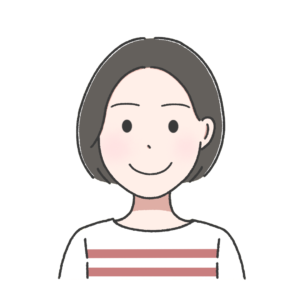
「旅行は必須!」という人もいると思うので、特別費に含める費目は人によって異なってくるかと思います。
家計管理方法の再構築
ステップ① 貯金の目標金額を決める
「1年間でどれくらい貯める」=「使わない金額」の目標を決めます。例えば「毎月3万円貯金」なら年間で36万円ということになります。
私の場合は毎月4万円を投資に回しているので、普通預金としては毎月1万円=年間12万円を残すことを目標にしました。
ステップ② 各費目を固定費・変動費・特別費に振り分ける
私の場合はこのような振り分けになりました。(家賃・光熱費は夫の口座から引き落とされています)
特別費以外にも、時々しか発生しない出費を見落とさないために独自に「変動費(不定期)」というカテゴリーを作ってみました。
当たり前ですが、失敗しない家計管理のためにはこの費目を洗い出す作業というのが重要になってきます。車検とか自動車税とか時々しか発生しない出費も徹底的に洗い出します。
| 固定費 | 自動車税、積み立て投資、子供の習い事、給食費・・・etc |
| 変動費(毎月) | 食費、日用品、おむつ、ミルク・・・etc |
| 変動費(不定期) | 交通費、美容室、子供の服、医療費、車検・・・etc |
| 特別費 | 旅行、レジャー、プレゼント、お年玉、おもちゃ、自分の服・・・etc |
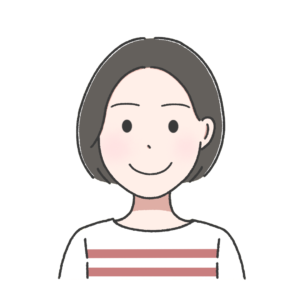
恥ずかしながら、この作業をやってみて初めて「1年を通しての出費を考える」ということをしました。これまでは毎月必ず発生する出費のことしか考えていなかったため、どう頑張っても家計管理が上手くいきませんでした。
ステップ③ 各費目の年間予算を決める
固定費も変動費も特別費もすべてひっくるめて、1年間でどれだけの出費になりそうかざっくりと予算を決めます。
そして、下記の計算がマイナスになるようであれば年間予算を見直します。
1年間の総収入 ー 年間予算 = 貯金額
ステップ④ 月ごとの予算を決める
ここでポイントとなるとは、月ごとの予算は毎月固定ではなくその月の予定を考慮して決めるということです。
たとえば旅行に行く月と行かない月では旅行代は大きく変わってきますよね?私の場合は他にも「プレゼント代」という費目を設けているので、家族の誕生日や父の日・母の日などのイベントがあるかどうかで予算が変わってきます。
月によっては収入よりも支出が上回る場合がありますが、年間予算を決めているので1年を通して見ると収支が合うようになっています(予算通りに行けば・・・ですが)。
ただ、普通預金に多少の貯金があることは前提になります。
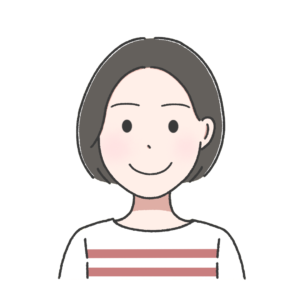
1月~12月の予算を一気に決める必要はありませんが、年の後半に足りなくならいようにバランスを考えて決めていきます。
ステップ⑤ 家計簿アプリに予算を設定する
あとは決めた予算を家計簿アプリに設定し、実際に運用していくだけです。
家計管理を見直してみて・・・(感想)

以前は物欲や楽したい気持ちに負けてついつい出費が増え、月末に足りなくなるということを繰り返していました。
なぜそんなグダグダな家計管理になっていたのかと考えてみましたが、おそらく「ちゃんと家計管理することのメリット」が見えていなかったからなのではないかと思います。
足りなくなっても貯金を少し下ろせばなんとかなるし、貯金は減ったり増えたりで底をつくということはなかったので大きく困ることもありませんでした。
でも今回、1年間の予想される出費をすべて洗い出してみて、「よし、今年は海外旅行に行く予定だからやりくり頑張ろう!」とか「車検に備えて毎月少しずつ積み立てておけば慌てないで済むな」とか、長いスパンで見た時の家計管理の目的が明確になりました。
まだ家計を見直してみて日が浅いので予算通りにいかなかったりなどあるかと思いますが、運用しながら調整していき、来年からは軌道に乗せていきたいと思います。